皆さんはロボットとはいつからあるのか知っていますか?そんな方に向けてこの記事ではなるべく分かりやすくロボットについて解説しようと試みました。この記事を読めばロボットについての理解が深まるでしょう。この記事前半では、ロボットの歴史後半では、ロボットの種類について解説しましたのでどうかお読みください。
ロボットの歴史
「ロボット」という言葉は、1920年に劇作家カレル・チャペックがチェコ語の労働を意味するロボタ(robota)という言葉から作ったと言われているが、彼自身は兄ヨゼフが作った言葉だと主張しているそうです。
詳しく知りたい方は⇩
カレル・チャペック – Wikipedia
ロボット工学三原則
また、1950年には、科学者でもありSF作家でもあったアイザック・アシモフがSF小説「われはロボット」の中で「ロボット工学三原則」を提唱し、その後のロボット研究者に影響を与えています。
第一条
ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危害を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
第二条
ロボットは人間に与えらえた命令に服従しなければならない。
ただし、与えられた命令が第一条に反する場合は、この限りではない。
第三条
ロボットは第一条および第二条に反するおそれのない限り、自己を守らなければならない。
このロボット工学三原則は聞いたことがある方もいるのではないでしょうか?ちなみにこの『われはロボット』には「ロビイ」「堂々めぐり」「われ思う、ゆえに・・・・・・」「野うさぎを追って」「うそつき」「迷子のロボット」「逃避」「証拠」「災厄のとき」の9編の短編が収録されています。面白いので、ぜひ読んでみてはいかがですか?
と、話はそれましたが引き続きロボットの歴史について解説します。
世界初の産業ロボット
世界初の実用化産業ロボットとは1960年代にアメリカ合衆国のユニメーションという名前の会社によって作られたユニメートというものです。
またこのユニメートは1967年には晴海の見本市で公開され、その後、日本の川崎重工でライセンス生産され、活躍しました。また、費用は1971年の時点でおよそ$25000ドルでした。ちなみに1971年のいわゆる「ニクソン・ショック」で明らかになったドル不安によって、1米ドル=308円に固定されたため、その当時の$25000とは7700000円(770万円)もしたそうです。
東洋初のロボット
東洋初のロボットは日本で作られました。それは學天則(がくてんそく)という名前で、1928年に昭和天皇即位を記念した大礼記念京都博覧会に大阪毎日新聞が出品した、東洋で初めてのロボットです。上部に告暁鳥と言う機械仕掛けの鳥が付属していて、この鳥が鳴くと學天則は瞑想を始めます。そしてひらめきを得ると霊感灯(インスピレーション・ライト)が光を放ち、それを掲げ、鏑矢型のペンでひらめきを文字に起こしたといわれています。
學天則という名は「天則(自然)に学ぶ」という生物学者らしい考えに基づいた命名だそうです。
ロボットの種類
ロボットの種類には大きく分けて産業用ロボットとサービスロボットの2つがあります。
産業用ロボット
産業ロボットとは工場で使われているような産業を自動化するためのロボットです。
また産業ロボットには直角座標型ロボット、多関節ロボット、双腕型、スカラロボット、パラレルロボットの5つがあります。
ここでは紹介しませんので詳しく知りたい方はご自身でお調べください。

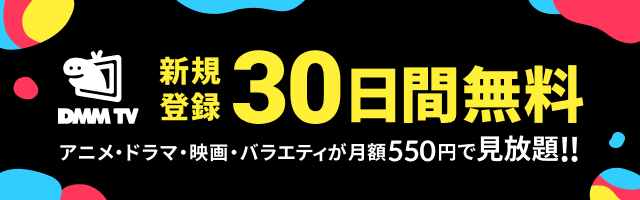



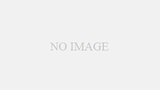
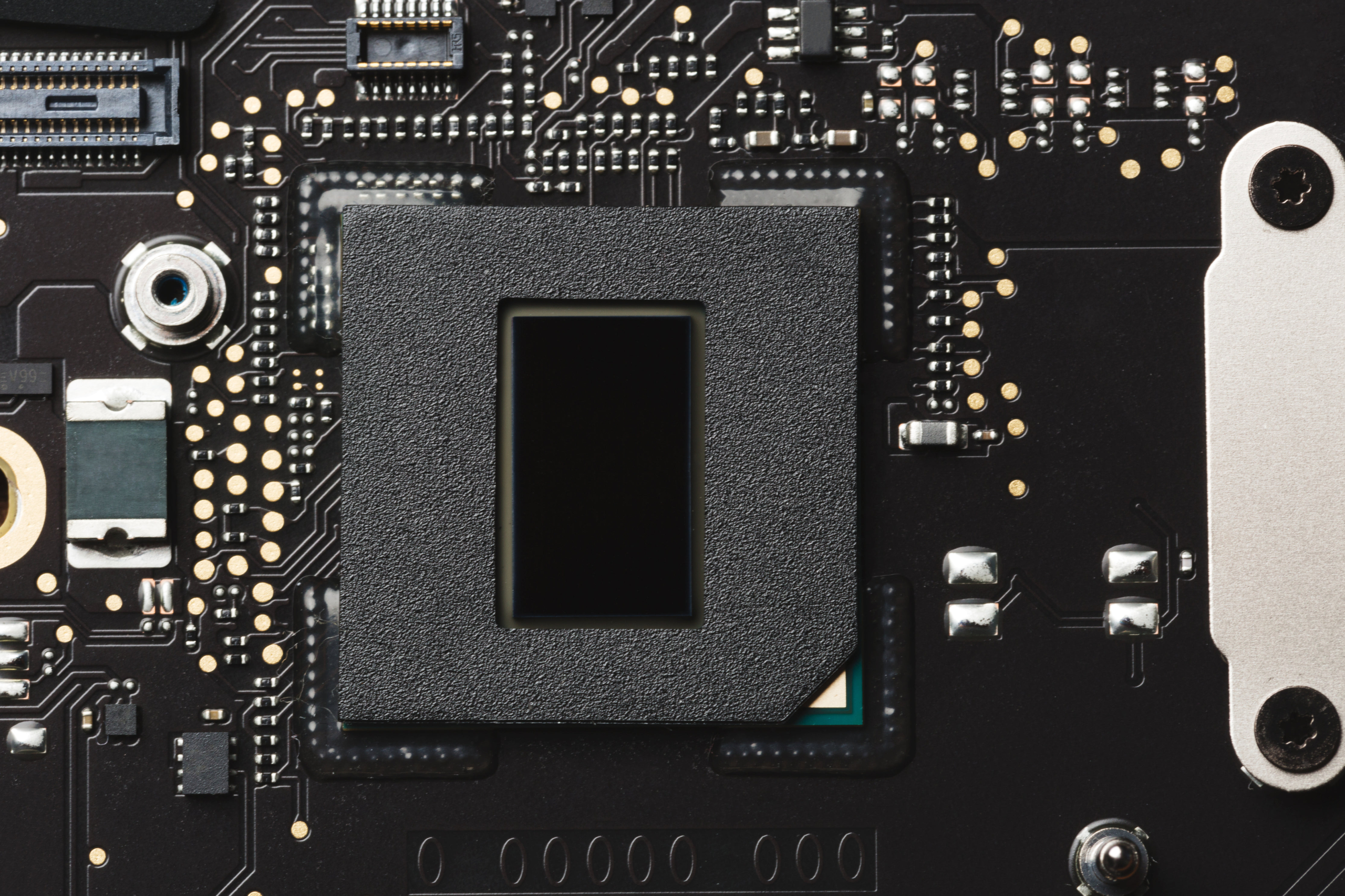
コメント